サステナビリティという言葉を聞いたことはありますか?
経営者や経営企画部などの担当者の方は耳にしたことのある言葉かもしれません。ここでは、サステナビリティの定義と意味や導入している企業の取り組み事例についてご説明します。
サステナビリティとは

そもそもサステナビリティとはどういう意味なのでしょうか。
サステナビリティの意味
サステナビリティとは広く環境・社会・経済の3つの観点から世の中を持続可能(機能やシステムを失わずに良好な状態を維持できるよう)にしていく、という考え方のことをいいます。特に企業が事業活動を通じて環境・社会・経済に与える影響を考慮して、長期的き企業戦略を立てていく取組のことはコーポレート・サステナビリティとも呼ばれています。
CSRとの違い
サステナビリティについて取り上げられる時には関連してCSRという言葉が取り上げられます。CSRは「corporate social responsibility」といい、直訳すると「企業の社会的責任」となります。
CSRの基本的な考え方としては、『企業はただ自社の利益を追及するだけでなく、顧客や従業員、取引先、投資家、その他全ての利害関係者からの要求にこたえるべきだ』というものになります。安心安全な製品提供や健康で働きやすい職場環境の整備に加えて、内外に対しての説明責任を果たす必要があったり、法令を遵守しなければならないという責任が含まれます。
つまり、サステナビリティとSCRの違いとしては方向性は同じであるものの、範囲を限定しているか否かの違いになります。サステナビリティは企業以外にも政府や自治体、団体や個人にわたる責任をさしますが、CSRは特に企業責任を指したい場合に用います。
サステナビリティの考え方
では、サステナビリティの考え方は大きく分けると次の2つです。
長期的視野をもつ
サステナビリティという考え方が一般的に普及する前は、多くの企業が短期的な利益に集中する傾向にありましたが、最近では「短期的な利益の追求は長い目でみるとかえって利益を損ねる」「結局は成功しない」といったサステナビリティに通ずる考えが一般的になっています。
CSRはコストではない
CSRはコストではないというのは海外企業では一般的な考え方になってきていますが、日本企業では「CSRはコスト」と考えられることが多いです。海外では「社会・環境への勝ち提供は将来的に利益になりえる」という考え方が広まっています。
CSRをコストと見ている企業は「善管注意義務違反」「受託者責任違反」になる可能性もあるようなので注意が必要です。
サステナビリティの分野範囲
サステナビリティが対象としている分野はとても広いので分かりにくいですが、GRIスタンダードでは企業が持続可能な経営のために考慮すべき分野を経済・社会・環境の3つから33テーマに分けています。(※GRIスタンダード:組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般に報告する際の、グローバルレベルにおけるベストプラクティスを提示するための規準)
サステナビリティ課題として考慮すべき点を把握して対策を考えましょう。
社会的観点(計19テーマ)
「雇用」「労使関係」「労働安全衛生」「研修および教育」「多様性と機会均等」「非差別」「結社の自由と団体交渉」「児童労働」「強制労働」「保安慣行」「先住民の権利」「人権評価」「地域コミュニティ」「サプライヤーの社会評価」「公共政策」「顧客の安全衛生」「マーケティングとラベリング」「顧客プライバシー」「社会経済コンプライアンス」
環境的観点(計8テーマ)
「原材料」「エネルギー」「水」「生物多様性」「大気への排出」「排水および廃棄物」「環境コンプライアンス」サプライヤーの環境評価」
経済的観点(計6テーマ)
「経済的パフォーマンス」「市場での存在感」「間接的な経済影響」「調達慣行」「腐敗防止」「反競争的行為」
サステナビリティ経営のメリットとは

サステナビリティ経営を行っていくうえで、メリットは何でしょうか。3つご紹介します。
ブランド価値の向上
サステナビリティ経営を行うことでブランド価値が向上します。
今の社会的風潮では環境問題や社会問題が注目されているなかで、企業も社会の一員としての対策が求められています。環境問題や社会問題の課題に対して企業が積極的に取り組む姿勢を示すことでブランド価値の向上につながります。
事業拡大
事業拡大につながる可能性もあります。メーカーであれば工場の二酸化炭素の排出量を抑える取組を行うなかで、技術の開発に成功して新サービスに繋がる可能性もあります。
あるいは貧困や飢餓といった社会問題に取り組むなかでソーシャルビジネスの事業領域開拓の可能性もあります。
従業員満足度の向上
企業側が従業員によって心地よい環境を提供することで従業員満足度につながり、より企業に対してコミットする効果も期待できます。やりがいも感じられることから従業員の定着率も上がる可能性があります。
サステナビリティの取り組み事例
サステナビリティに取り組んでいる企業事例をご紹介します。
日産
日産自動車は、環境や社会的テーマに関連して「Nissan Sustainability 2022」という取組をしています。自動車業界は従来から、自動車の排出ガスが地球温暖化や空気汚染の原因になっているとして対策が求められてきました。
そのなかで日産は開発を進めて、2022年までに新車からの二酸化炭素排出量を2000年度比で40%削減を目標に掲げています。ほかにも生産や企業活動で排出される二酸化炭素や化学物質の目標も掲げています。
ユニクロ
ユニクロはプランネット、ピープル、コミュニティを3本の柱として「服のチカラを、社会のチカラに。」という宣言を掲げています。
プランネットとは、素材選びやエコバックの普及によって持続可能性を追求する環境負荷を削減する服作りを意味しています。
ピープルは労働者が働きやすい環境づくりにするため、人権の尊重、安心かつ安全な労働環境の確保、ダイバーシティの推進を行っています。
コミュニティはリサイクル活動や難民への物資的支援に取り組むことで社会との調和や関わりを指しています。
スターバックス
スターバックスは調達、環境、コミュニティ、文化といった観点からサステナビリティに取り組んでいます。特に調達では「エシカル調達」という物を掲げており、品質基準を設定して、基準を満たしている原料を調達すること、生産者や生産地域に対してフェアトレードを守ること、生産者の労働環境を守り生産性向上を支えることなどを重視しています。
さらに、事業での環境負荷を低減するためにリサイクルや紙コップ削減などを推進しています。
イケア
イケアは素材選びと気候・環境の点で独自のサステナビリティの取り組みを行っています。素材については、イケアがこだわっているのは管理された森林の木材を調達することです。これにより品質やデザイン性に優れているだけでなく、環境保護にも貢献しています。
気候・環境については、節水や省エネルギーにつながる製品作りや廃棄物削減への取組を掲げており、消費者に対してサステナブルな暮らしの形を提案しています。
NEC
NECは原材料・雇用においてサステナビリティの取り組みを行っています。
原材料においては、食品ロスや廃棄、過剰な生産や売れ残りによる無駄な資源・輸送エネルギー消費を解消するために、在庫情報や販売情報をAIを活用したデータ流通基盤を共有し、バリューチェーン全体で需給を最適化します。
また、製造業側の在庫・生産の最適化や卸売業・物流業の在庫の最適化、リソースの効率化をすることで雇用を適切にし、労働力不足を解消する取組を掲げています。
サステナビリティを行っている企業へのイメージ

では、実際にサステナビリティを行っている企業に対して消費者はどのようなイメージを持っているのでしょうか。
ブランドに対して持つイメージ
サステナビリティの取り組みを行っている企業に対して、実施していることを認知している人は「好感が持てる」「社会に貢献している」という印象を持っています。ほかにも「独自性がある」「社会の変化に対応が早い」「国際的/グローバルな視野がある」「成長力がある」「応援したい」といった良いイメージを持っていました。
参照:Intage調査結果
情報を得るタイミングとは
消費者が企業が行っているサステナビリティの取り組みに関して情報を得るタイミングとしては「テレビで見る」「新聞や雑誌の記事を読む」といったマスメディアからの情報取得や「WEB上の記事で読む」という回答が多いようです。企業の取り組みを消費者に発信する場合は、マスメディアを活用すると良いでしょう。
参照:Intage調査結果
サステナビリティを意識して企業ブランドの向上を図りましょう
いかがでしたでしょうか。サステナビリティという言葉自体を聞いたことがない人も企業が取り組んでいる事例を知ると内容をイメージしやすいのではないでしょうか。
サステナビリティの取り組みについて検討している場合は、行動指針の目的をもって活動していきましょう。マスメディアを活用することで消費者の目にも触れられ、社会的信用向上とともに企業ブランドの向上を図ることが出来ます。
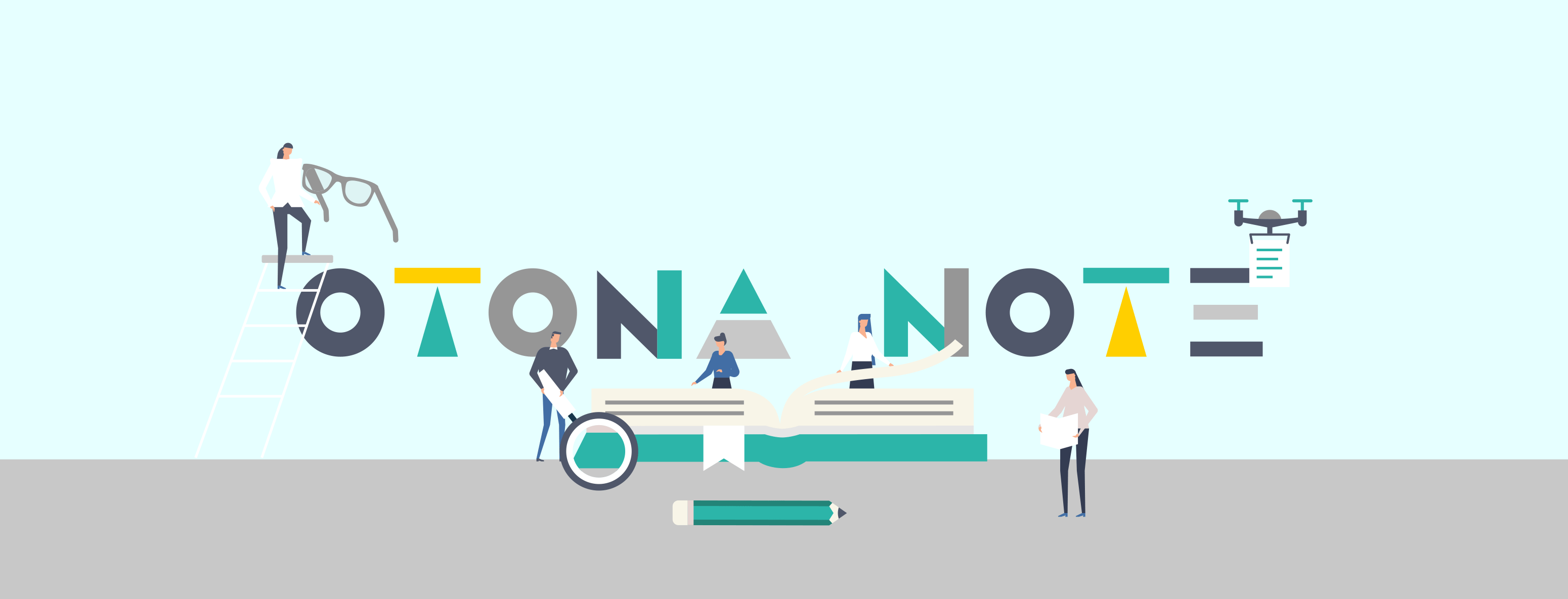



コメント